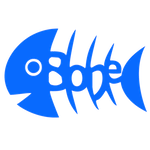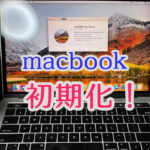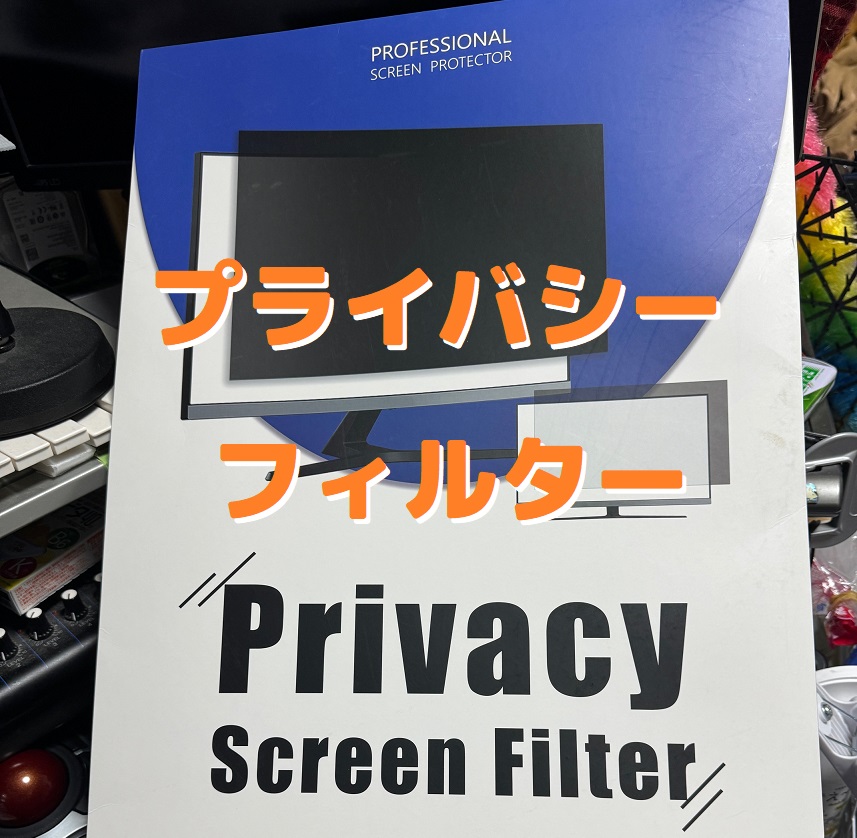この記事のカテゴリー
オーディオインターフェースにおける通信規格
■USB2とUSB3の違い
RMEさんの製品は今もUSB2.0端子が搭載されている機器が目立ちます。
私が所有しているUFX販売時にはUSB3.0も普及してきてはいたのですが、なぜか2.0規格にこだわっていたのです。
理由は通信面的にUSB2.0で必要十分であり、一番普及し安定している規格だからとあります。
USB2と3の違いがあるならば、それは情報量になるといいます。
しかし、通常利用範囲のクオリティー、チャンネル数であれば2.0でも余裕があるそうで現在販売されているUFX+という
最大96chの録音ができるインターフェースのみにUSB3とThunderboltt端子が搭載されている形になっています。

■レイテンシー
コンピューターを使用していると必ず起こる弊害がレイテンシー(遅延時間)となります。
録音する場合、音がインターフェースを通りパソコンに送られます。その結果の音が今度はパソコンからインターフェースに戻り、ヘッドホンやスピーカーに流れてくるのです。
この行って帰ってくるのに遅延が必ず起きる。これがレイテンシー(遅延)となるのです。
ミックス作業では問題なくてもボーカルや楽器を録音する時に、その結果を機器ながら録音するとレイテンシーがいかに重要かがわかってきます。
楽器を演奏しても少し音が遅れて聞こえる。ダブリングのように自分の声がわずかにディレイして聴こえる。
なんとも作業がしづらくなるのです。
人間の耳はあいまいでもあり鋭くもあるのですが、このレイテンシーを短くして何とか録音に差し支えのない状態がほしいのです。
最近のインターフェースにはこれを防ぐため「ダイレクトモニタリング」という戻ってくる音を遮断して録音に特化するモードもあります。
欠点はDAWのエフェクターが使えない点です。
ボーカル録音の場合、とくにダイレクトだと生々しすぎて歌いづらい。できればうっすら空間系のリバーブエフェクタをかけると歌い易くなるのに。
となるわけですが、ただでさえレイテンシーが気になるのにエフェクタを挟むとよりエフェクタ分の演算が起きるのでレイテンシー数値が増える。
そこで高価なインターフェースにはDSPと呼ばれる処理部品が搭載され、PCに負担をかけずにエフェクタをかける事ができるようになった製品もあるのです。
商業で使われるProtools HDやUltimateが高いのはこのDSPが大量に使われており、多くのチャンネルにDSP用エフェクタが使えるようになっています。
■各規格によるレイテンシーの違い
RMEさんの説明によるとUSB2にしてもThunderboltにしても、送れる情報量の違いだけで速度的にはわずかな差と説明されています。
しかしレイテンシーとはこのわずかな差が影響してくるのです。
人間が感知できるレイテンシーは2ms以上からと言われています。
つまり2ms以上の時間が長くなってくると違和感を感じはじめ、4ms以上になると明らかに遅延を感じはじめるというのです。
レイテンシーを抑えるには色々方法がありますが、やはり一番のポイントは通信速度が関係してくるようです。
そこでインターフェースメーカーはUSB3やThunderbolt端子を搭載させてレイテンシーが短くできるようにしているのです。
■実際のレイテンシー違い
レイテンシーはインターフェース自体の処理能力にも関係しているので、同じUSB2.0でもメーカーの違いにより多少の誤差があるかと思いますが、それを抜きにした結果です。
以下は96kHzでの作業時におけるレイテンシーです。
USB2.0・・・・・2.47ms
USB3.0・・・・・2.22ms
Thunderbolt ・・1.67ms
USB2.0と3.0は同一インターフェースの結果であり、Thunderboltに関しては違うインターフェースとなっている。
たしかにUSB2.0と3.0は数値的にはわずかな差ではありますが、人間の感知できるレイテンシーが2ms以上からとなっているので、
この両者はすでにそれを感知できるレベルの数値であることから、このわずかな違いが重要になってくる事になります。
感知できても、それを許容できるか出来ないかの違いがレイテンシー数値の鍵になるのです。
さて、このように今回は96kHz時のレイテンシー数値になるのですが、より高解像の192kHzにすると更にレイテンシーを縮める事ができるのです。
実際にUSB2.0のレイテンシー差は96kHz時は2.47msですが、192kHzになると1.82msとなるのです。
USB3.0では更に差があり96kHz時は2.22msですが、192kHzでは1.23msとなるのです。
2msを超えることがないので感知できない。または感知しづらい状態になるようです。

といった感じに、もしレイテンシー対策で困った場合は例えばボーカル録音のような場合は、一時的に解像度を上げたフォーマットで録音するという手もあるかと思います。
もちろんパソコンの能力に依存してくるとは思いますが対策の1つだと思います。
またレイテンシーに重要なのはDAWソフト側のバッファーの調整でも減らす事ができます。
これも低くしすぎると遅延は小さくできますがパソコンの動作が安定しなかったり、ノイズがでてきたりとするので限界があります。
ちなみにですが、USB2.0の場合はバッファサイズが128を下回ると不安定になってきますが、Thunderboltでは一番低い32を設定できてしまうなんて話もあります。
通信速度がより早くなるということは、もしかしたらDAW内でエフェクタを挟む事も夢ではなくなってくるのかもしれません。
このバッファの数値でも実はUSB2.0と3.0,Thunderboltでは安定度が違ってくる事になるそうです。
総合的に、このわずかな違いがあるからこそ、通信規格は重要なポイントでもあると言えることが分かってくるかと思います。