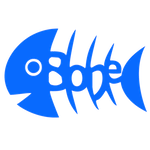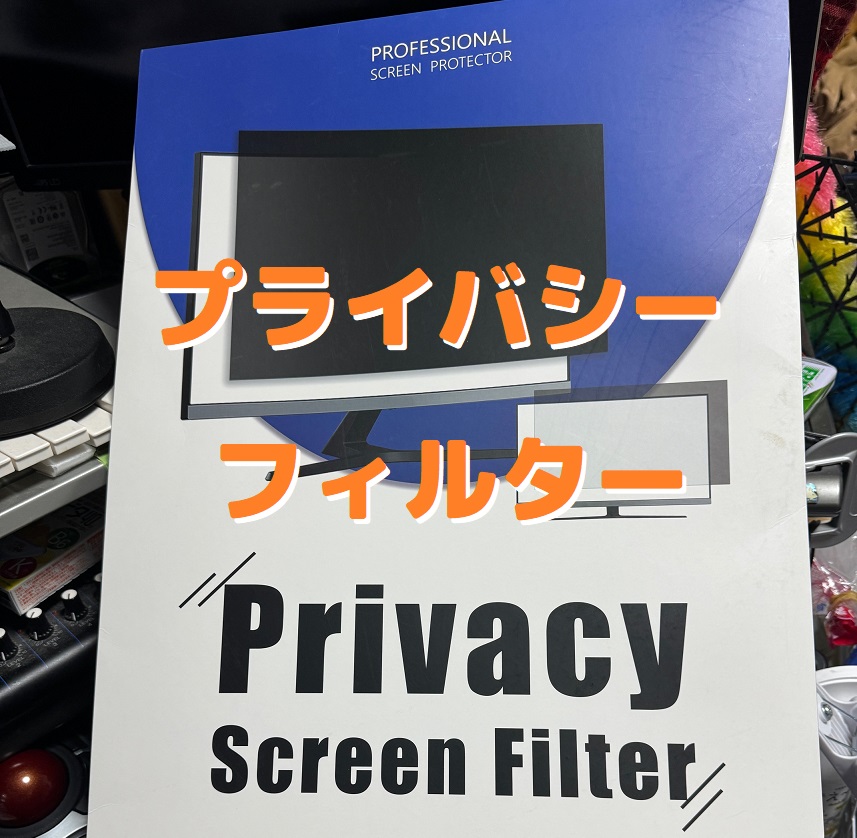この記事のカテゴリー
音の頭分け
今回は音の「頭分け」についてです。
頭分けとは文字通り、1つの回線を頭で分ける。
二つに割るという意味となります。
マイク回線を分けるとき、一方はPAへ、一方はオーディオ収録用にと分ける場合があります。
ホールの様な施設の場合、頭分けを頼むとマルチボックスに分かれた音声を送ってもらうことが出来ます。
ただ、ファンタムを使うようなコンデンサーマイクの場合は会場側から流してもらいましょう。
もし自分の機器からファンタムを流す場合は、直でマイクへ流し、自分の機器から会場へ回線を返します。
個人的な環境で頭分けをする場合はマルチボックスのような大掛かりな物でなくても大丈夫です。

頭わけをするには「Yケーブル」を使用すればいいのです。
キャノン(xlr)仕様のYケーブルがありますので、それをダイナミックマイクの後に接続すれば、
そこからPA,自分の機器への頭分けができます。
サウンドハウスで手に入るクラシックプロのYケーブルであれば¥300円程度で手に入ります。
何かの時に便利ですのでYケーブルは所有しておいてもよいかと思います。
また、ミキサーからバスアウトでもらうことも出来ますので、頭分けによるトラブルを避けたい場合はバスアウト
できる環境であれば、そちらでもよいかと思います。
頭分けを嫌がる施設もありますので、バスアウトか頭分けか、どちらが良いかを聞いてみて反応を確かめるのが気持ちよく
作業が遂行できるかと思います。
もし会場へマイク音声を返す場合は相手の音響機器にあった「+4」で返すこともお忘れなく。
その場合も念のため「+4」で返しますと伝えるのもお忘れなく^^